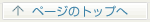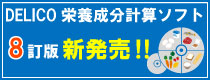バレンタインデーの変化
インフルエンザが猛威を振るっています。正月明けは病院前に患者の列ができる程で、警報レベルの都道府県の数は36となったそうです。
手洗いやうがい、消毒、マスクの着用、人ごみを避けるなどして予防・対策を徹底して十分に気を付けて下さい。
さて、私事なのですが学生時代からの旧友が結婚することとなり、学生の頃を思い出して昔を懐かしむ機会がありました。
2月はバレンタインというイベントで教室全体がソワソワした空気感にありました。懐かしい青春の思い出です。
調べてみると、バレンタインデーの起源は諸説あるようですが、その一つとして聖バレンタイン殉教説というものがあります。
3世紀ローマでは、戦争に出陣する為、若者の結婚が禁止されていたようで、その状況に憂いたバレンタインという名の司祭が密かに若者を結婚をさせていました。
それが見つかり皇帝から迫害を受け、バレンタイン司祭は2月14日に命を落としました。その後、その司祭を祀り祈りを捧げたのがバレンタインデーの始まりとされています。(※1)
日本ではバレンタインデーは百貨店などが行ったキャンペーンから「女性から愛する男性へチョコレートを贈る日」として定着していきました。
「本命チョコ」や「義理チョコ」などの言葉が生まれ、現在では「自分チョコ」「友チョコ」など日本ならではのイベントとして今日に至ります。
ホワイトデーではバレンタインデーでチョコレートをもらった相手へ返すお菓子に、それぞれ意味があるようで、さらに独自性を持ち進化したように思います。(筆者は全く知りませんでした。)
気になりましたので、少しピックアップしてみました。
—————————————————————————————————-
・マカロン
…あなたは特別な存在
・キャンディー
…あなたのことが好き
・バウムクーヘン
…幸せがずっと続く様に
・マドレーヌ
…あなたともっと仲良くなりたい/特別な関係
・キャラメル
…一緒にいると安心できる
・クッキー
…友達でいよう
・チョコレート
…もらった気持ちをお返しします/あなたの気持ちは受け取れません
・ホワイトチョコ
…今まで通りの関係を望みます/嫌いじゃないけど友達のままでいよう
(※2)
—————————————————————————————————-
上記にもある通り、ホワイトデーでチョコレートを返した場合は、もらった気持ちをそのまま返すということで「あなたの気持ちは受け取れません」という意味になってしまうようなので注意が必要とのことです。
しかしながら、チョコレートにはカカオポリフェノールという成分が含まれており、様々な効果が期待できます。
日本チョコレート・ココア協会によると、チョコレートに含まれるカカオポリフェノールの効果には、動物試験ではあるものの、ピロリ菌の胃内への定着抑制、多くの下痢原生細菌に対しての抗菌効果、そしてインフルエンザウイルスの感染抑制効果があるようです。(※3)
インフルエンザが流行り出すのは12月~3月頃で、バレンタインデー・ホワイトデーがこの期間に納まっていることは無論偶然だと思いますが、チョコレートに含まれる成分にインフルエンザの予防効果があるとは驚きです。
ホワイトデーでチョコレートをプレゼントしたとしても、受け手が有識者であれば「身体を大事に」という想いが込められていると考えてもらえるかもしれません。
ですが、チョコレートは医薬品ではありませんし、あくまで予防ですのでチョコレートを食べたからといって絶対にインフルエンザにかからないとは言えません。食べ過ぎにも注意が必要です。
ただ、研究によって健康に役立つ様々な食材の情報が認知されていくことは良いことですので、これからも食材に関する新たな情報の発見には注目したいところです。
日本特有のおもてなし精神や贈答文化・返礼の習慣が相まって、今日の日本のバレンタインデーへと変化したと考えると、これらのイベントは日本文化と言い切ってしまっても過言ではないと思います。
将来、上記のような食品やそれらの原料の成分における新たな効果の発見、ジェンダーフリーや既成概念にとらわれないような考え方などが加味されて、日本のバレンタインデーがより進化していくのでは?と想像すると、今後どのようなイベントに遷移していくのか楽しみです。
参考文献
※1 バレンタインデーの秘密 著:浜本隆志
※2 阪急阪神百貨店公式通販サイト https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/lifestyle/detail/001443.html
※3 日本チョコレート・ココア協会 http://www.chocolate-cocoa.com/lecture/q10/07/