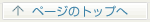食に関する本
暑い日々もようやく終わり、秋の気配を感じるようになってきました。
秋となるとなぜか「食欲の秋」だとか「スポーツの秋」だとか「芸術の秋」とか言われ、
なぜ「~の秋」なのか強引に感じるものもありますが、とにかくこれにかこつけて、
売る気満々の棚を眺めることも楽しさの一つではあります。
中でも個人的にオススメなのが書店です。
「読書の秋」にちなんで特集を組んでいる書棚を見ると、
なかなかセンスのあるチョイスをしており、タイトルを眺めているだけで楽しい気分にさせてくれます。
というわけで、今回のこの「読書の秋」にちなみ、食に関する本を5冊紹介させていただきます。
「火の賜物 ヒトは料理で進化した」 リチャード・ランガム(著) 依田卓巳(翻訳)
ヒトと動物を隔てるもの、その一つが火を使うか否か、です。
そしてこれまでの通説では、「ヒトが進化したことにより、火を扱うようになった」ということになっています。
しかし、果たしてそうなのか?実際はその逆ではないのか?
つまり「火を使って食材を加熱調理したことにより、ヒトが進化した」という推論をこの本では読むことができます。
食材を焼いて柔らかくしたことで歯・顎が縮小して頭蓋骨が変形。消化時間を短くできたので胃腸が縮小。
消化エネルギーを脳に回せるようになったため、頭蓋骨に合わせて脳が進化。
火を扱えるようになったので獣を怖がる必要性はなくなり、地上生活を始めた。
さらにエネルギーの効率化は移動距離を延ばすことになり、人類大移動をもたらした、といった感じです。
アダムとイブは禁断の果実を食べ、知識を得たことで楽園を追放されますが、
この禁断の果実こそが焼いた食材であったと考えると、すべて辻褄が合いますね。
「家畜化という進化 人間はいかに動物を変えたか」 リチャード・C・フランシス(著) 西尾香苗(翻訳)
家畜・・・英語では「livestock」つまり「生きた在庫」と言われますが、
この家畜の発明なくして、人類は現在の肉体を手に入れられなかったと言っても過言ではありません。
しかし、食べられるために生まれてくる家畜の側からすればそれはどうなのでしょう?
実は彼らは「自ら家畜になることを選択した」のです。
例えば最も古い家畜であるイヌは、オオカミが家畜化されたものです。
オオカミの中から人間の周りをうろつき、その食べ残しに有り付くことを憶えた種が現れ、
それらは安定的に食べ物を得られるようになったため、野生の種よりも多くの子孫を残した。
さらに、そのオオカミをヒトが飼うようになり、おとなしい種だけを何世代もかけ合わせ、イヌが誕生した。
そしてこの手法を他の動物にも適合させ、家畜化が進んでいきます。猫、牛、豚、馬、羊、山羊・・・
現在、家畜産業は曲がり角を迎えていますが、見つめ直す意味でも、読んで損はない一冊です。
「スパイス、爆薬、医薬品 世界史を変えた17の化学物質」 ジェイ・バーレサン(著)ペニー・ルクーター(著・編集) 小林力(翻訳)
スパイスが金や銀と同等の価値を持ち、人々が一攫千金を夢見て大海原へと繰り出した大航海時代。
しかし、これは単に何かを見つける旅でありませんでした。
その後に起こる人や物質を含めた大きな化学反応を起こす旅だったのです。
しかもそれは芋づる式に連なるように発見・開発されていきます。
この本では、スパイスを皮切りに、17種の化学物質が世界を変えていく様が紹介されています。、
「スパイス」を求めての大航海時代、その大航海時代で悩まされた壊血病を克服した「アスコルビン酸」、
新大陸での奴隷労働によって作り出された「グルコース」「セルロース」・・・
そして、とある化学構造の変化なくして、ここまで人類は進化はなかっただろうという最終章。
17種すべてが食ではありませんが、その多くが何らかの形で食に関連しています。
化学物質を歴史に沿って紹介しつつも、どこか小説のような巧みな構成に関心させられる一冊です。
「保存食品開発物語」 スー・シェパード(著) 赤根洋子(翻訳)
肉は家畜が殺された時から、野菜は茎や枝や地面から引き抜かれた時から、それらは腐り始めます。
農耕や牧畜を始めただけでは不十分で、同時に食の保存技術を確立しなければなりませんでした。
シンプルな乾燥から始まり、塩蔵、酢漬け、燻製、糖漬け・・・と様々な保存技術が確立されてきました。
そして日々の糧に頭を悩ますことがなくなった人類は、歴史や文化の形成に大きく関与するようになります。
大航海時代などは保存食がなければ到底実現できませんでした。
しかしその保存食も、おいしさを求められるようになると、もはや料理人では対応できなくなります。
そこへ現れたのがパスツールを筆頭とした科学者たちです。
彼らが細菌学を持ちんだことで、保存技術はもう一段進化し、それは今も保存食の基礎となっています。
この本では、そういった先人たちの苦労、そしてその過程で引きおこされたで多数の犠牲を知ることができます。
「食品偽装の歴史」 ビー・ウィルソン(著) 高儀進(翻訳)
食品偽装事件が後を絶ちませんが、それは別に珍しいことではなく、昔から存在していました。
古代ローマでワインに混ぜられた鉛。中世英国で白パンにするために混ぜられたミョウバン。
これらは無知であるがゆえのことだと考えると、多少目をつむれないこともありません。
しかし、産業革命がおこってからは、その食品偽装が大々的に行われるようになります。それも確信犯的に。
産業革命は人々を都市へと流入させましたが、そこで食べるものといえば、
これまで農村で食べてきた顔の知った誰かが作ったものではなく、
誰か知らない人が作ったものを食べなければなりませんでした。
そこへ儲け主義が介入し、数々の悲惨な食品偽装が行われていくことになったのです。
本書では背筋が寒くなるような食品偽装例が紹介され、多数の人命が失われてきたことを知ることができます。
そして、なぜ英国の食が不味くなったのかが、よくわかりました。
英国では相互監視の役目を果たしていたギルド制が他国よりも早くに廃れ、
それは産業革命を推し進めた原動力でもありましたが、不味い食に国民が慣れてしまうことでもあったのです。
どの本も300~400ページとボリュームがありますが、秋の夜長にゆっくりと読んでみてはいかがでしょうか。